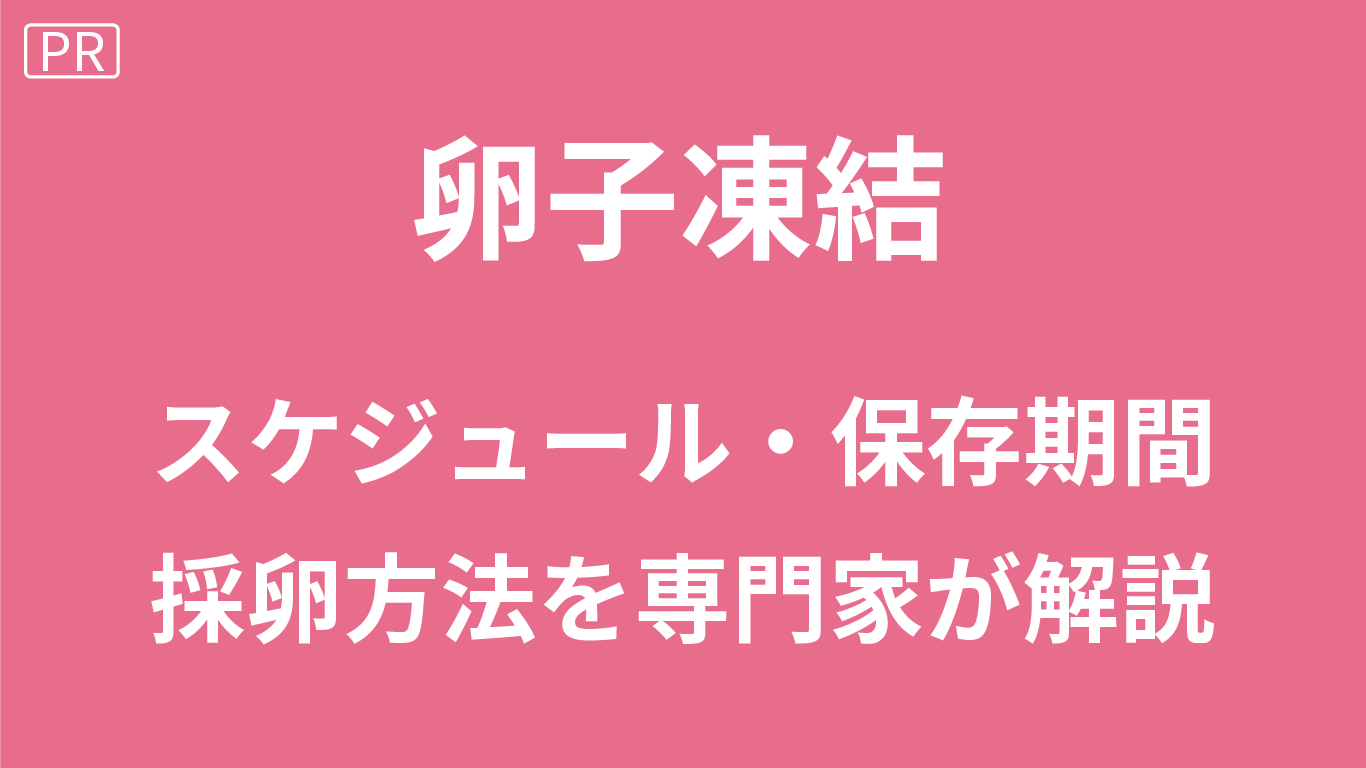人生の選択肢を広げられる卵子凍結ですが、気になるのは「仕事や普段の生活と卵子凍結は両立できるの?」という点です。
卵子凍結を始めるなら、全体のスケジュールや通院回数、凍結卵子の保存期間について知っておく必要があります。
本記事では、そんな卵子凍結の具体的なスケジュールや卵子の保存期間、全体の通院回数について詳しく説明していきます。卵子凍結を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。
しかし、妊娠前~妊娠初期は1日あたり640μgほどの葉酸(茹でたほうれん草5束分相当)が必要とされており、食事だけでカバーしようとすると栄養バランスが偏ったり、コストがかさんだりする可能性があります。
そんな時におすすめなのが葉酸サプリ「mitas」です!1日あたり100~200円程度で妊娠期に大切な栄養素をしっかり摂れるので、卵子凍結前に体内の葉酸濃度を上げることができます。

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、スギ薬局売上No.1*と絶大な人気を誇っています。
厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
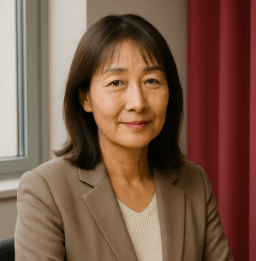
江川 美穂
不妊治療の専門家兼NPO法人日本不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラー。大学卒業後、不妊治療に興味を持ち、不妊治療を研究している医療機関を徹底的に調査して分析。自身も不妊治療を経験し、現在は一児の母。

原田 美由貴
自身も不妊治療を経験。「子どもを授かりたい」という強い思いから、不妊治療に特化した数多くの医療機関を受診。体外受精やホルモン治療など、さまざまな治療法に取り組んできた実体験をもとに、不妊に悩む方々に寄り添う記事を執筆。現在は二児の母。
卵子凍結のスケジュール・流れ
一般的に、卵子凍結は以下の4つの段階に分けて行われます。
- 診察・検査
- 排卵誘発
- 採卵
- 卵子凍結
それぞれの処置について詳しく確認していきましょう。
診察・検査
卵子凍結をすることが決まると、まず診察・検査が行われます。
検査は血液検査、超音波検査などがあり、ホルモン値や卵巣機能、卵子の数(AMH値)を調べるために行われます。この検査結果を基にスケジュールが決まり、今後はそれに従って通院や自己注射などを行うことになるのです。
なお、各医療機関の混雑度合いにもよりますが、検査には2~3時間程度かかる可能性もあります。そのため、初診の際はできるだけ時間に余裕を持って来院するのが良いでしょう。
排卵誘発
診察・検査が終わると、良質な卵子を採取するために排卵誘発剤を使用する段階に入ります。
排卵誘発剤には注射や内服薬といった様々な種類があり、年齢や卵巣機能などを考慮しながらその人に合った方法が選ばれます。排卵誘発の際には副作用が出ることもあるため、不調を感じた際はすぐに担当医・看護師に相談してください。
なお、排卵誘発は卵胞の発育具合によって薬剤の量を調整するため、数回ほど通院する必要があります。通院希望日があれば必ず医師に伝え、できるだけ無理なく通院できるようスケジュールを調整していきましょう。
採卵
排卵誘発が完了すると、いよいよ採卵の段階に入ります。
採卵では、膣から超音波機械を挿入し、卵巣の中の卵胞に針を刺して卵胞液とともに卵子を吸引します。人によっては痛みを感じることがあるため、不安な方は精脈麻酔を使用できないか担当医に相談しておくと良いでしょう。
なお、採卵は体に一定の負担がかかる処置となります。そのため、採卵後はできるだけ無理をせず、安静にしておくことをおすすめします。
とはいえ、通院理由を公にできず、仕事を休めないという方も多いはずです。そういった方は事前に終了予定時刻を確認し、極力予定の変更が難しいアポイントは入れないようにしておくと良いでしょう。
卵子凍結
採取された卵子はその後、マイナス196℃の液体窒素で凍結保存されます。
なお、冷凍保存の期間は各医療機関によって異なります。規定の期間以上保存する場合は別途更新料が必要となる点に注意が必要です。
凍結卵子の保存期間は妊娠可能な年齢まで
卵子凍結は、採取した卵子を液体窒素タンクに入れて凍結保存する方法です。この時に使用される液体窒素タンクは、理論上永久に卵子を保存できると言われています。
しかし、多くのクリニックは卵子の保存期間を「満50歳まで」と定めています。これは、妊娠には年齢の限界があり、50歳以上の妊娠には高いリスクがあるためです。
また、一般社団法人日本生殖医学会が発表している「社会的適応による未受精卵子あるいは卵巣組織の凍結・保存のガイドライン」では、40歳以上の卵子凍結、45歳を超えて凍結した未受精卵子の使用は推奨されていません。
卵子の質は年齢を重ねると共に劣化し、流産率も高まっていきます。卵子凍結をする場合はできるだけ若いうちに行い、45歳までに顕微授精・胚移植のステップに移ることをおすすめします。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績
卵子凍結にかかる通院回数は一般的に6~7回
卵子凍結では、初診なども含めた全体の通院回数は6~7回程度とされています。実際に、通院スケジュールのモデルケースを見てみましょう。
| 回数 | 所要時間 | 来院時期 |
|---|---|---|
| 1回目(初診) | 2~3時間 | 特に指定なし |
| 2回目(採卵周期) | 約2時間 | 月経開始から3日以内 |
| 3回目(採卵周期) | 約2時間 | 月経開始から7~9日目 |
| 4回目(採卵周期) | 約2時間 | 月経開始から10~12日目 |
| 5回目(採卵) | 午前中いっぱい | 月経開始から12~14日目 |
| 6回目(採卵後の診察) | 約1時間 | 医師から指定 |
なお、上記はあくまでモデルケースであり、体調や卵子の状況によって必要な通院回数は左右されます。卵子凍結にかかる期間は2~3週間と仮定し、その上でスケジュールを組むと良いでしょう。
長期間保存していた凍結卵子を使うと妊娠のリスクは高くなる?
前述したように、液体窒素で凍結保存された卵子は半永久的に保存され、その質が劣化することもありません。
そのため、もし30歳の時に卵子を凍結保存しておけば、40歳で「妊娠したい」と考えた際に30歳の状態の卵子を使用できるのです。つまり、保存期間の長さと卵子の質に相関性はないと言えます。
また、凍結卵子を使用した妊娠であっても、染色体異常や先天性異常、発達障害といったリスクが他の不妊治療方法や自然妊娠と比べて増えることはありません。
ただし、卵子凍結を使用した場合は受精率・胚盤胞率(受精から5日間順調に発育する確率)が低下する傾向にあります。採卵時の年齢が高いほど受精率も下がるため、できるだけ若いうちに卵子凍結を行うのが良いでしょう。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績
卵子凍結のスケジュール・通院回数・保存期間に関するQ&A
卵子凍結のスケジュール・流れを把握しよう【まとめ】
卵子凍結は約6~7回の通院で採卵から冷凍保存までを行うことができます。
「仕事や家庭と両立できるか不安」という方も多いかもしれませんが、最近では土日診療やオンライン相談といった柔軟な対応を取っているクリニックも増えてきたため、担当医としっかり相談することで無理なく卵子凍結を行えます。
また、自治体・会社によっては卵子凍結に関する補助金や福利厚生制度を利用できる場合もあります。負担を減らしつつ卵子凍結を行うためにも、まずは制度を調べ、自分のスケジュールに合ったクリニックを選ぶようにしてくださいね。
神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。
ただし、体の中に十分な葉酸を蓄えるにはおよそ1か月ほどかかります。つまり、妊娠に気付いたタイミング(多くは妊娠5〜6週目)から飲み始めても、必要な量に間に合わないかもしれません。
そのため、妊活サプリ売上No.1*の「mitas(ミタス)」で今のうちから葉酸を摂ることをおすすめします!

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。
1日あたり100~200円程度で必要な栄養素をしっかり摂れるので、まずはmitasを試してみてはいかがでしょうか。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績