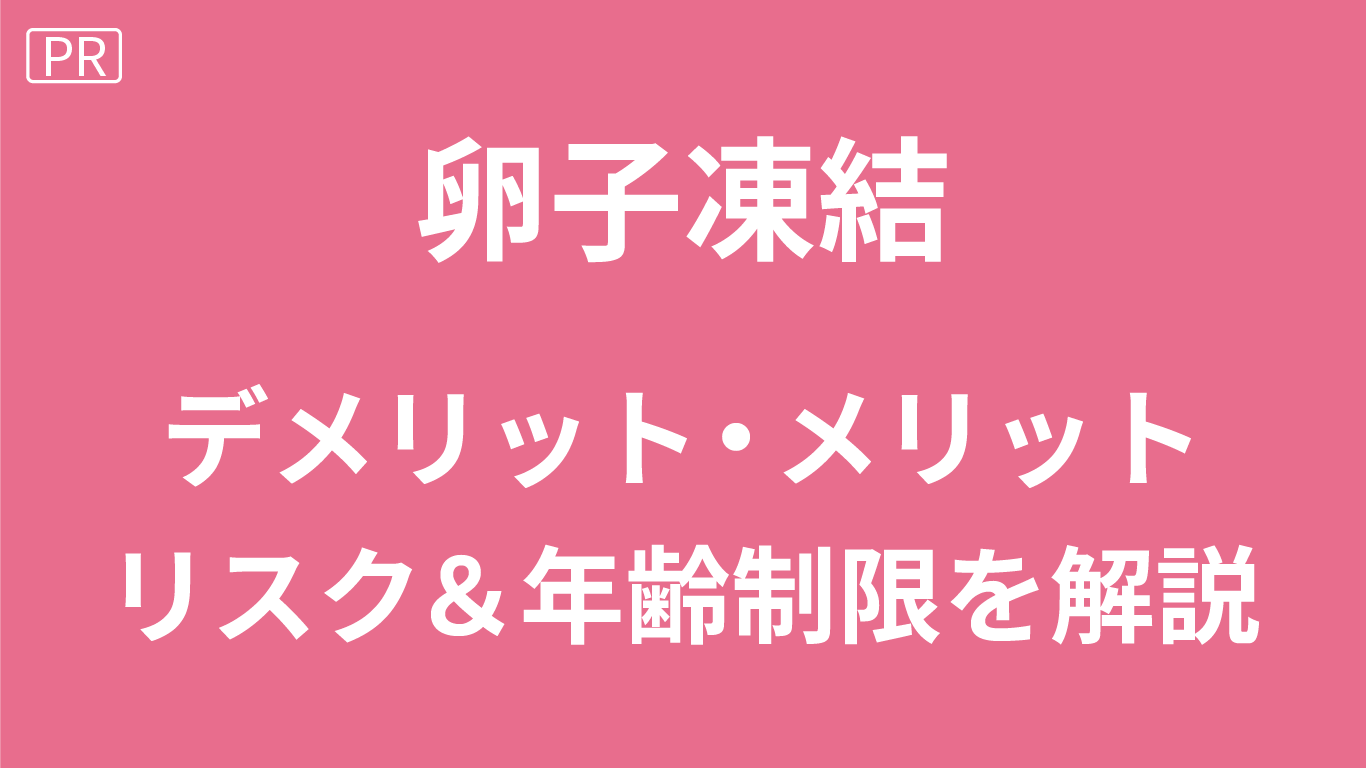卵子凍結は、将来の妊娠や体外受精に備えて、若いうちに卵子を採取・凍結保存しておくことです。
女性のキャリア形成やパートナー探しのタイミングを合わせられることで注目を集めていますが、卵子凍結にはデメリットもあります。むしろ、デメリットを事前に理解しておかなければ、大きなリスクを背負う可能性もあるのです。
本記事では、そんな卵子凍結のメリット・デメリットや年齢制限、卵子凍結の副作用・合併症のリスクを詳しく解説します。卵子凍結に少しでも興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。
しかし、妊娠前~妊娠初期は1日あたり640μgほどの葉酸(茹でたほうれん草5束分相当)が必要とされており、食事だけでカバーしようとすると栄養バランスが偏ったり、コストがかさんだりする可能性があります。
そんな時におすすめなのが葉酸サプリ「mitas」です!1日あたり100~200円程度で妊娠期に大切な栄養素をしっかり摂れるので、卵子凍結前に体内の葉酸濃度を上げることができます。

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、スギ薬局売上No.1*と絶大な人気を誇っています。
厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
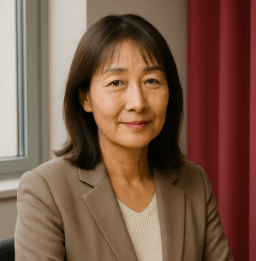
江川 美穂
不妊治療の専門家兼NPO法人日本不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラー。大学卒業後、不妊治療に興味を持ち、不妊治療を研究している医療機関を徹底的に調査して分析。自身も不妊治療を経験し、現在は一児の母。

原田 美由貴
自身も不妊治療を経験。「子どもを授かりたい」という強い思いから、不妊治療に特化した数多くの医療機関を受診。体外受精やホルモン治療など、さまざまな治療法に取り組んできた実体験をもとに、不妊に悩む方々に寄り添う記事を執筆。現在は二児の母。
【卵子凍結のデメリットを知る前に】卵子凍結は35歳までに行うのがベスト
卵子凍結とは、将来の妊娠・出産に備えて卵子を採取・凍結保存することです。近年は、東京都が少子化対策の一環として卵子凍結費等を新年度予算に計上するなど、個人・自治体に関わらず注目が集まるようになりました。
そんな卵子凍結ですが、多くの医療機関は「40歳前後まで」を対象としています。また、東京都、山梨県、大阪府の卵子凍結助成金を受け取れるのは、39歳までの女性です。
基本的に、妊娠率を維持できるのは34歳までであり、35歳を過ぎると卵子の質は低下すると言われています。そのため、卵子凍結をするなら35歳までに行うのが良いでしょう。
卵子凍結を35歳以上で行う場合のリスク
35歳以上の方が卵子凍結を行う場合、卵子の質の低下を補うため、より多くの卵子を採取する必要があります。採取する卵子が多ければ多いほど費用もかかるので、様々な面で負担が大きくなってしまうのです。
また、一般社団法人日本生殖医学会が発表している「社会的適応による未受精卵子あるいは卵巣組織の凍結・保存のガイドライン」では、40歳を超えての卵子凍結および、45歳を超えて凍結した未受精卵子の使用は推奨されないとしています。
卵子凍結は自分らしい人生を歩むための有効な手段となり得ますが、それを活用するには早くから行動しておかなければなりません。人生の可能性を広げたいなら、できるだけ若いうちに卵子を凍結保存するのが良いでしょう。
卵子凍結のメリット
卵子凍結には、以下の3つのメリットが存在します。
- 妊娠・出産の時期をコントロール可能
- 若い卵子を保存できる
- 加齢により減少する卵子を保存できる
それぞれ順番に解説していきます。
妊娠・出産の時期をコントロール可能
1つ目は「妊娠・出産の時期をコントロール可能」という点です。
卵子は凍結保存しておくことで、将来自分が望んだ時期で融解し、顕微授精で妊娠できます。
つまり、「今はキャリア形成に専念したい」「将来的に子どもが欲しいけれど、今は育児が難しい」という方でも、妊娠という選択肢を諦めることなく生活できるのです。
また、女性は加齢によって妊娠率が低下しますが、あらかじめ若い卵子を凍結保存しておけば、当時の妊娠率を維持が期待できます。ライフプランに合わせて柔軟に対応できるので、人生の選択肢を残しておきたい方は卵子凍結を行うことをおすすめします。
若い卵子を保存できる
2つ目は「若い卵子を保存できる」という点です。
若いうちに採取した卵子と高齢で採取した卵子では、若い卵子の方がミトコンドリアの機能や卵子の質が高いと判明しています。
また、高齢の卵子の場合は妊娠率の低下、流産率の上昇が見られることもあり、将来妊娠・出産を望むなら若いうちに卵子を採取することが推奨されているのです。
自分の望むタイミングで妊娠・出産したいと考えている方は40歳、可能であれば35歳までに卵子凍結を行うと良いでしょう。
加齢により減少する卵子を保存できる
3つ目は「加齢により減少する卵子を保存できる」という点です。
卵子は出生時に200万個、20歳までに12万個、30歳時点で5万個、40歳には5,000個と減少の一途をたどります。さらに、残された卵子は年齢に伴って老化するので、妊孕性も大きく低下していくのです。
現在、卵子の質そのものを高める方法は、残念ながら発見されていません。そのため、卵子凍結を行いたいと考えているならば、加齢によって卵子の質が低下するまでに凍結保存しておく必要があります。
なお、卵子凍結を行う際は必ずクリニックにご相談の上、費用も含めてシミュレーションを行いましょう。後述するデメリットやリスクも把握した上で、「本当に卵子凍結をするべきか」を今一度考えてみてくださいね。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績
卵子凍結のデメリット
卵子凍結は人生の選択肢を広げることができますが、以下の5つのデメリットも存在します。
- 誰でも卵子凍結ができるわけではない
- 卵子に大きなストレスがかかる
- 100%妊娠を保証するものではない
- 体に負担がかかる
- 卵子凍結の料金は高い・保険適用なし
それぞれ順番に解説していきます。
誰でも卵子凍結ができるわけではない
1つ目は「誰でも卵子凍結ができるわけではない」という点です。
前述したように、卵子凍結は40歳以上の採取が推奨されていません。また、たとえ40歳未満で採取したとしても、45歳以上での凍結卵子を利用した妊娠も推奨されていないのです。
このように、卵子凍結には一定の年齢制限がかかっています。各クリニックによって対象年齢は異なるため、事前にご確認の上、卵子凍結を行いましょう。
卵子に大きなストレスがかかる
2つ目は「卵子に大きなストレスがかかる」という点です。
卵子は凍結することにより、質が低下する可能性があります。さらに、一度凍結してから融解して受精する方法は、卵子がダメージを受けることもあるのです。
卵子の質が低下した場合、受精や受精卵の発育に悪影響を及ぼす恐れがあります。卵子凍結をする際はこれらのリスクをしっかりと理解しておきましょう。
100%妊娠を保証するものではない
3つ目は「100%妊娠を保証するものではない」という点です。
卵子凍結は将来の妊娠・出産に備えられる方法ですが、必ず妊娠できるわけではありません。融解した卵子が受精できる状態でなければ妊娠できないのはもちろん、着床後に流産してしまうリスクも存在します。
また、採取後の卵子はマイナス196℃の液体窒素で冷凍保存されますが、予期せぬトラブルや災害によって傷ついたり、質が低下したりする可能性もあります。こういった場合に備えて、各クリニックの返金規定などを確認しておくことも重要です。
卵子凍結はあくまで将来の妊娠の可能性を高めるためのものです。体、メンタル、経済的に負担の大きい選択肢であることを理解した上で行うようにしてください。
体に負担がかかる
4つ目は「体に負担がかかる」という点です。
通常、卵子凍結をする際は排卵誘発剤を用いて採卵します。この時、副作用として卵巣過剰刺激症候群が起きる可能性があり、最悪の場合、肺梗塞・脳梗塞などを発症することがあるのです。
このように、卵子凍結はその過程の中で様々な副作用、合併症のリスクが存在します。そのため、あらかじめ治療内容やリスクを確認し、必ず信頼できる医師に相談してから卵子凍結を開始することをおすすめします。
卵子凍結の料金は高い・保険適用なし
5つ目は「卵子凍結は保険適用されない」という点です。
卵子凍結は保険適用外となっているので、全額自費診療となります。
医療機関によって費用は異なりますが、低く見積もっても卵子凍結だけで40万円程度の資金が必要だと考えておきましょう。なお、妊娠までの総額費用は100万円前後が一般的です。
卵子凍結の副作用・合併症のリスク
前述の通り、卵子凍結には副作用・合併症のリスクが伴います。具体的には、以下の4つのリスクが挙げられます。
- 出血
- 麻酔によるアレルギー症状など
- 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
- 妊娠合併症
それぞれ順番に解説していきます。
出血
卵子凍結では、卵子を採取する際に膣から卵巣に向けて細長い針を刺します。この時、卵巣から出血が起こるケースがあるのです。
基本的に出血は少量かつ、自然に止まることが多いですが、場合によっては止血・輸血が必要になることもあります。
さらに、針を刺した部分から細菌が入り、感染症を引き起こすリスクも存在します。ただし、こういった輸血・止血が必要な出血や感染症は非常に稀なケースです。
麻酔によるアレルギー症状など
卵子凍結では、採卵時に麻酔を行うことで採卵の痛みを軽減します。この時、麻酔薬に対するアレルギー症状やじんましん、喘息といった静脈麻酔の副作用が出る可能性があるのです。
副作用が起こるケースはあまり報告されていませんが、100%起こらないという確証もありません。これまで麻酔を使用した際にアレルギー症状が出た方、息苦しさなどを感じたことがある方は、必ず事前に医師に相談するようにしてください。
卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
卵巣過剰刺激症候群(らんそうかじょうしげきしょうこうぐん:別名OHSS)とは、排卵後に卵巣が腫大し、おなかに水がたまったり、重症の場合は血栓症を引き起こしたりする疾患のことを指します。
この卵巣過剰刺激症候群は、排卵誘発剤をはじめとした卵巣刺激治療によって引き起こされることがあるのです。
こちらも発症するケースは稀ですが、万が一重症化した場合は腎不全・肺梗塞に繋がる恐れもあります。治療後、体調が悪くなった場合は無理せず安静にし、症状が気になる場合には診察を受けるようにしましょう。
妊娠合併症
凍結卵子を使用して妊娠した場合、自然妊娠と比較すると妊娠糖尿病などをはじめとした妊娠合併症の発祥リスクが高くなるとされています。
分泌前出血や妊娠高血圧症候群といった合併症のほか、帝王切開分娩や早産、低出産時分娩などのリスクも上がるため、十分な注意が必要です。
なお、これらの妊娠合併症は移植時点での年齢が高齢になるほど発症リスクが高いことが報告されています。卵子凍結を行う方はこれらのリスクを考慮し、その上で計画を立てるようにしてください。
受精卵凍結の場合も副作用・合併症のリスクはある?
受精卵凍結も未授精卵凍結と同様に、排卵誘発剤による卵巣過剰刺激症候群が発症したり、採卵による出血が起こったりする可能性があります。
ただし、これらはある程度予防ができるので、こういったケースが起こることは非常に稀です。
また、受精卵凍結の場合は未受精卵凍結に比べ、融解の際に質が低下しにくく、妊娠率も比較的高いことが報告されています。未受精卵凍結よりも負担が少ないため、既婚の方、パートナーがいる方は受精卵凍結をおすすめします。
卵子凍結のメリット・デメリットに関する質問
卵子凍結のメリット・デメリットとは?医師に相談してリスクに備えよう
卵子凍結は若い卵子を保存することで、妊娠・出産の時期をコントロールできる方法です。
しかし、卵子凍結には体への負担や高額な費用、採卵時のリスクなど、様々なデメリットがあります。特に、35歳以上の卵子凍結、45歳以上の卵子凍結を用いた妊娠には一定のリスクが付きまとうことは知っておかなければなりません。
将来の選択肢を増やすことだけでなく、自分自身の健康を守るためにも、メリットとデメリットを比較することは非常に大切です。その上で卵子凍結をすべきか検討し、不安がある場合は医師に相談することでリスクに備えていきましょう。
神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。
しかし、妊娠前~妊娠初期は1日あたり640μgほどの葉酸(茹でたほうれん草5束分相当)が必要とされており、食事だけでカバーしようとすると栄養バランスが偏ったり、コストがかさんだりする可能性があります。
そんな時におすすめなのが葉酸サプリ「mitas」です!1日あたり100~200円程度で妊娠期に大切な栄養素をしっかり摂れるので、卵子凍結前に体内の葉酸濃度を上げることができます。

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、スギ薬局売上No.1*と絶大な人気を誇っています。
厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
※【ミタス売上No.1の表記について】スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績