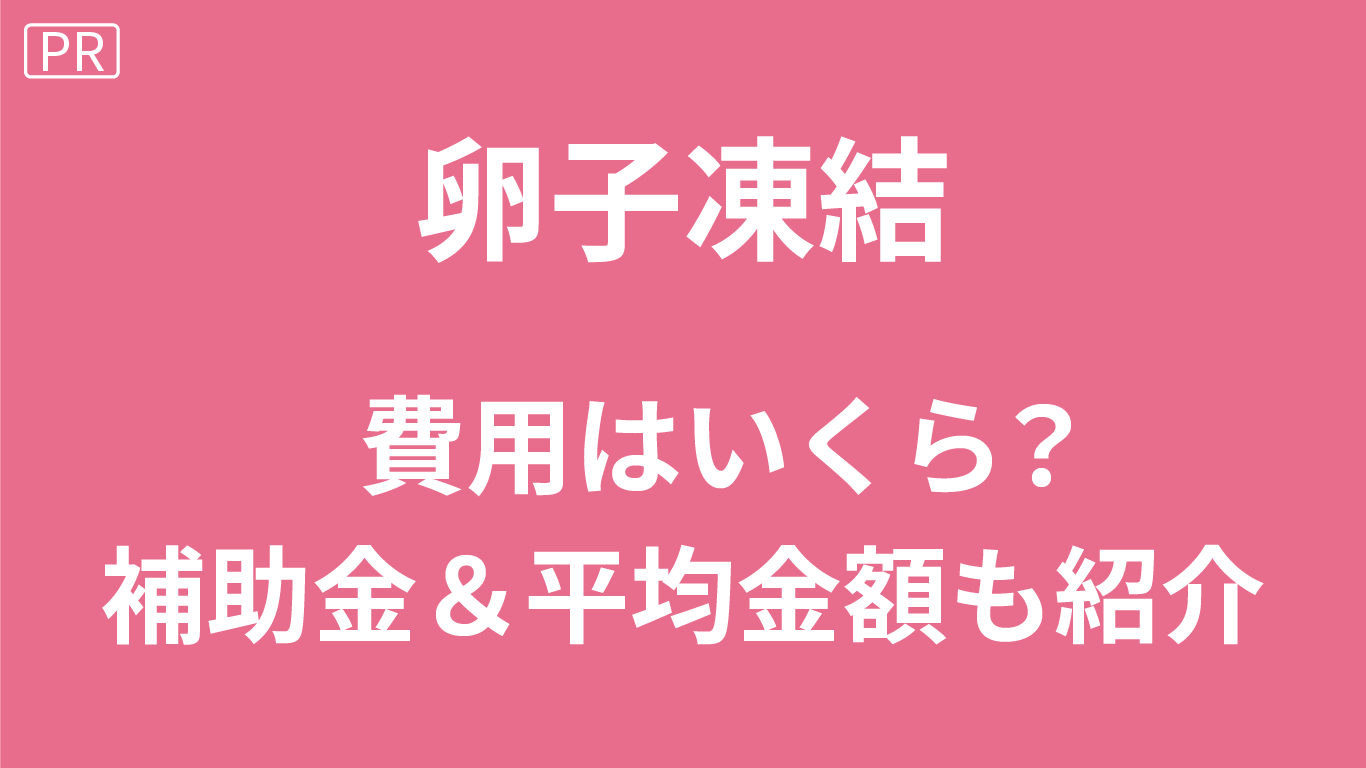近年、女性の社会進出が進む中、仕事に追われて結婚や出産・パートナーについて考える時間が取れないと感じる方もいらっしゃるでしょう。また、病気などにより妊娠率が低下することについて悩みを抱えている方もいるかもしれません。
そういった問題に対して、卵子凍結は将来の選択肢を広げる有効な方法の1つとなり得ます。
本記事では、卵子凍結の概要や費用、スケジュールについて詳しくご紹介していきます。また、自治体による助成金制度や卵子凍結に伴うリスクについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。
しかし、妊娠前~妊娠初期は1日あたり640μgほどの葉酸(茹でたほうれん草5束分相当)が必要とされており、食事だけでカバーしようとすると栄養バランスが偏ったり、コストがかさんだりする可能性があります。
そんな時におすすめなのが葉酸サプリ「mitas」です!1日あたり100~200円程度で妊娠期に大切な栄養素をしっかり摂れるので、卵子凍結前に体内の葉酸濃度を上げることができます。

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、スギ薬局売上No.1*と絶大な人気を誇っています。
厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
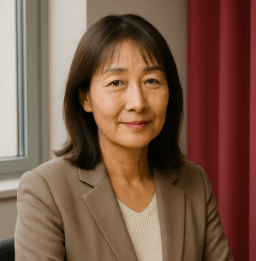
江川 美穂
不妊治療の専門家兼NPO法人日本不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラー。大学卒業後、不妊治療に興味を持ち、不妊治療を研究している医療機関を徹底的に調査して分析。自身も不妊治療を経験し、現在は一児の母。

原田 美由貴
自身も不妊治療を経験。「子どもを授かりたい」という強い思いから、不妊治療に特化した数多くの医療機関を受診。体外受精やホルモン治療など、さまざまな治療法に取り組んできた実体験をもとに、不妊に悩む方々に寄り添う記事を執筆。現在は二児の母。
卵子凍結とは
卵子凍結(未受精卵凍結)とは、将来の妊娠・出産に備えて若いうちに卵子を採取・凍結保存することです。卵子凍結は「社会的適応」か「医学的適応」のどちらかに該当する場合に行われます。
社会的適応による卵子凍結
卵子凍結の「社会的適応」とは、個人のライフスタイルや将来の選択肢を広げるために行われるケースを指します。
近年、日本では女性の社会進出に伴い、妊娠・出産の時期が遅くなる傾向が見られます。「子どもが欲しいとは思うけれど、今はキャリアを優先したい」「親の介護があり、育児は難しい」といった理由で、妊娠のタイミングを見送る方もいらっしゃるでしょう。
妊娠・出産に最も適しているとされる年齢は20~30代ですが、加齢に伴い卵巣機能は徐々に低下していきます。しかし、妊孕性が高いうちに卵子凍結を行うことで、加齢による妊孕性の低下を補い、高齢でも妊娠できる可能性が高くなるのです。
卵子の質に関しては、卵子の質を上げるにはで詳しく解説しています。
医学的適応による卵子凍結
卵子凍結の「医学的適応」とは、病気や治療で妊娠が難しくなるリスクのある女性が、将来の妊娠の可能性を保つために行うケースを指します。
例えば、がん治療に伴う化学療法や放射線治療、卵巣機能低下症、遺伝性疾患などが原因で妊孕性が低下すると予測される場合は、この適応に該当します。
こういった治療を受ける若年女性が将来的に妊娠を希望する場合は、専門の医師と相談しながら最適なタイミングで卵子を採取・凍結します。治療の開始時期や健康状態を踏まえて計画が立てられるので、安心して治療に臨むことが可能です。
一部の自治体では卵子凍結の費用を補助する助成金制度が設けられています。具体的な助成内容・適用条件については、各自治体のホームページや医療機関にてご確認ください。
卵子凍結のメリット
卵子凍結の最大のメリットは、高齢になっても妊娠できる可能性を維持できることです。
女性は加齢に応じて妊娠率が低下し、それに反して流産率は上昇していきます。こういったことが起きるのは、卵子に染色体異常が生じ、細胞分裂の失敗が起こりやすくなるからです。
また、卵巣内の卵子が少なくなると、薬を使用しても卵巣の反応が鈍くなる・卵子の発育が乏しくなる可能性もあります。
しかし、若いうちに卵子を凍結保存しておけば、将来妊娠を希望する際、加齢の影響を受けていない卵子を体外受精に用いることができるのです。
なお、卵子凍結の必要性は人それぞれです。卵子凍結はあくまでライフプランに合わせた選択の1つであり、必ずしなければならないものではありません。
ご自身のライフプランや健康状態、費用面の負担を考慮しながら、医師と相談して決めることをおすすめします。
卵子凍結の流れ・スケジュール
卵子凍結は、以下の流れで行われます。
- カウンセリング・検査
→ 血液検査・超音波検査などを行う。 - 排卵誘発
→ 卵子採取のために内服薬・注射などを使用して卵巣を刺激し、複数の卵子を育てる。 - 採卵手術
→ 卵巣に針を刺して卵子を採取する。 - 凍結保存
→ マイナス196℃の液体窒素で凍結保存を行う。
なお、卵子凍結にかかる期間は約2週間から3週間、通院回数は合計で5回程度とされています。健康状態や医療機関によって所要時間は異なるため、カウンセリングの際に確認しておくことをおすすめします。
卵子凍結の妊娠率
卵子凍結からの妊娠率は、凍結時の年齢や健康状態、凍結した卵子の数などに大きく影響されます。具体的な妊娠率や凍結の成功目安は以下の通りです。
| 融解後の卵子生存率 | 90~97% |
|---|---|
| 受精率 | 71~79% |
| 着床率 | 17~41% |
| 胚移植あたりの臨床妊娠率 | 36~61% |
| 融解卵子1個あたりの臨床妊娠率 | 4.5~12% |
論文によって数に差はありますが、共通するのは凍結時の年齢が若いほど妊娠率も高くなるということです。とはいえ、1個の卵子が妊娠する確率は低いため、若年女性の方も多くの卵子を凍結保存しておくことを強くおすすめします。
卵子凍結の知っておくべきリスクと注意点
卵子凍結は将来的な可能性を広げてくれる治療ですが、以下のようなリスクや注意点も存在します。
- 100%妊娠できるわけではない
- 凍結・融解した際に卵子がダメージを受ける
- 排卵誘発剤による単層過剰刺激症候群(OHSS)のリスクがある
- 卵子凍結は全額自費診療
- 妊娠・出産には年齢の限界が存在する
- 自然災害などによって永久保存できない可能性がある
不妊治療は医療の中でも成功率が高くない分野と言われています。卵子凍結の結果は個人差が大きく、決して妊娠・出産を確約するわけではありません。
これらのリスクをきちんと理解し、「本当に自分には卵子凍結が必要なのか」を真剣に考えることは、卵子凍結を行う上で非常に重要です。まずは各医療機関や自治体が開催する卵子凍結説明会に参加し、卵子凍結について理解を深めましょう。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /
公式サイト:https://shop.naturaltech.jp/
※スギ薬局の2024年7月妊活サプリ売り上げ実績
卵子凍結の費用はいくら?平均は40万円【保険適用はなし】
卵子凍結は保険適用外の治療法とされており、全額自費診療となります。
具体的な費用は各医療機関によって異なりますが、大まかな費用とそれの内訳は以下の通りです。
| 初診(検査・診察) | 30,000円~40,000円 |
|---|---|
| 採卵費用※ | 100,000円~250,000円 |
| 卵子凍結費用 | 200,000円~ |
| 卵子凍結更新料(卵子1個あたり) | 11,000円 |
| 総額(参考価格) | 350,000円~600,000円 |
医療機関によっては、採卵費用・卵子凍結費用を卵子の個数に関わらず、一律としている場合もあります。また、卵子凍結更新は1年毎であったり、3年毎であったりと異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
なお、卵子凍結後に顕微授精、胚(受精卵)移植を行った場合は別途料金がかかります。卵子凍結にかかる費用の平均は低く見積もっても約40万円、妊娠までの総額費用は数百万円以上かかると想定しておくことをおすすめします。
卵子凍結の補助金・助成金を紹介
卵子凍結にかかる費用は高額ですが、自治体による助成制度を利用すれば、費用面での負担を軽減しつつ不妊治療に臨むことが可能です。
ここからは、卵子凍結にかかる費用への助成を行っている自治体やその概要について詳しくお伝えします。
卵子凍結助成の対象となる方・要件【医学的適応の場合】
全国の自治体は、小児・AYA世代のがん患者の方を対象に、卵子凍結の助成制度を設けています。具体的な対象要件は各自治体によって異なりますが、共通する主な要件は以下の5点です。
- 申請時、提出先の都道府県に住所を有していること
- 対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方
- 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
- 指定医療機関から妊孕性温存療法を受けることおよび国の研究への臨床情報などの提供をすることについて説明を受けた上で、本事業に参加することについて同意した方
- 原疾患の治療内容について、以下のいずれかに該当する方(※下記に記載)
原疾患の治療内容の詳細
- 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
- 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
→乳がん(ホルモン療法)など - 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
→再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血など)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症など - アルキル化剤が投与される非がん患者
→全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病など
上記の条件をすべて満たし、必要書類を漏れなく提出すれば助成を受けることができます。なお、申請期限は全自治体で共通して、「卵子凍結に係る費用の支払い日の属する年度内(3月末まで)」です。
ただし、やむを得ない事情がある場合は翌年度の申請も可能です。その場合は、各自治体の申請窓口にご相談ください。
卵子凍結助成の対象となる方・要件【社会的適応の場合】
東京都・山梨県・千葉県柏市・大阪府では、社会的卵子凍結に対する助成金制度が設けられています。各自治体が公開している対象要件は下記の通りです。
- 採卵日において18~39歳の女性
- 東京都が開催する、卵子凍結の正しい知識を持っていただくための説明会に参加すること
- 説明会への参加申し込み日から助成金を申請するまでの間、継続して都内に住民登録をしていること
- 説明会への参加から1年以内に、都が指定する登録医療機関において、採卵準備のための投薬を開始すること
- 未受精卵子の採卵または凍結後、都が実施する調査に協力すること
- 凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供および海外への移送はいかなる場合も行わないこと
- 卵子凍結後も都が実施する調査に対し、継続的に協力すること(最大5年)
- 他の法令などの規定により、医療給付や費用助成を受けていないこと
どの地区でも、補助を受けるためには申請前に必ず説明会へ参加する必要がある点に注意が必要です。各要件をしっかりと確認し、その上で助成金を申請するようにしてください。
卵子凍結にかかる助成額
卵子凍結にかかる助成額は、医学的適応の場合と社会的適応の場合で異なります。具体的な金額は下記の通りです。
| 対象となる治療 | 1回あたりの助成上限額 |
|---|---|
| 胚(受精卵)凍結に係る治療 | 35万円 |
| 未授精卵子凍結に係る治療 | 20万円 |
| 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) | 50万円 |
卵子凍結には高額な費用がかかりますが、助成制度を活用することでその負担を多少なりとも減らせます。
現在、社会的卵子凍結に対する助成制度は全国で3箇所でしか設けられていませんが、今後他の都道府県・自治体が追随する可能性もあります。
卵子凍結をしたい方は助成が始まる可能性に備え、オンライン説明会などに参加することをおすすめします。
卵子凍結にかかる費用はいくら?質問と回答
卵子凍結の費用・値段が気になる方は無料カウンセリングを【まとめ】
卵子凍結は、女性のライフプランの選択肢を広げられる1つの手段です。
未婚・既婚に関係なく、「自分らしく生きるためには」と考える時、仕事・結婚・妊娠は必ず直面する壁となります。そんな時、若いうちに卵子凍結を行っていれば、妊娠・出産に関わる不安や焦り、後悔を少しでも減らせるかもしれません。
ただし、「すべての女性が卵子凍結をすべきか」と問われると、決してそうではありません。卵子凍結は体、精神、経済的に負担の大きい選択でもあります。
まずは無料カウンセリングや卵子凍結についてのセミナーに参加し、正しい知識を得ることが大切です。納得のいく人生の選択ができるよう、具体的なライフプランを立て、本当に卵子凍結が必要かを改めて考えてみてはいかがでしょうか。
神経管閉鎖障害(赤ちゃんの脳の一部が欠ける・背骨から脊髄が出る等)の対策として、医師や厚生労働省は妊娠前に十分な葉酸を摂取して葉酸濃度を高めるよう勧めています。
しかし、妊娠前~妊娠初期は1日あたり640μgほどの葉酸(茹でたほうれん草5束分相当)が必要とされており、食事だけでカバーしようとすると栄養バランスが偏ったり、コストがかさんだりする可能性があります。
そんな時におすすめなのが葉酸サプリ「mitas」です!1日あたり100~200円程度で妊娠期に大切な栄養素をしっかり摂れるので、卵子凍結前に体内の葉酸濃度を上げることができます。

mitasは不妊治療の専門医が監修している葉酸サプリで、スギ薬局売上No.1*と絶大な人気を誇っています。
厚生労働省の推奨する栄養素を100%配合しているうえ、和漢素材による温活力で、妊活の大敵である「ひんやり」対策にも役立つと言われています。
\ 【売上No.1】厚生労働省推奨の栄養100%配合 /